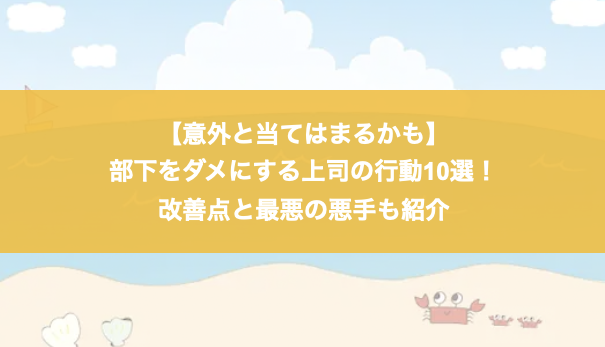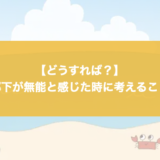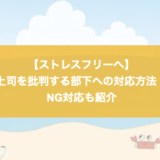部下を持つ上司の一つな大切なミッションとして、部下の育成というのはかなり重要ですよね。
部下が育って高パフォーマンス出してくれるようになったら、組織の業績も上がっていきますし。
しかし、自分の行なっている育成方法が正しいのか、、、ダメにしてないか、不安になることもありますよね。
そんなわけで、今回は部下側の視点も含め【ダメにする上司】について見ていきます。
また最後には【部下にとってのいい上司】についても書いてありますので、よければ最後まで読んでいってくださいね!
Contents
部下をダメにする上司の特徴9選

それでは早速部下をダメにする上司について見ていこうと思います。
後半では逆にどうすれば良いかも書いていきますので、是非読んでいってください!
それでは、どうぞ。
感情的に部下を叱りつける

最初は【感情的に部下を叱りつける】です。
書かないといけないレベルか?と思いつつも、意外とやっちゃってる人いるんですよね。
しかもみんなの前で叱りつけられたら、もう本当に最悪です。
部下のメンツはボコボコにされ
【俺もう、、、ここにいたくねーわ、、、】
となります、まぁ言われなくてもわかりますよね笑
中には

と、肯定している方もいますが、、、基本的には絶対に避けなければいけないやり方です。
部下を過剰に甘やかてしてしまう
続いては、部下を過剰に甘やかしてしまう、です。
辛そうにしている部下をついつい助けてしまいたく気持ちができますが、、、
ここで回答をパッと渡してしまうと部下の成長には中々繋がりません。
部下から見ると決して悪いというわけではないのですが、成長という意味では助けになっていないというわけですね。
【そんなことまで?】過干渉すぎる

続いては【過干渉すぎる】と言うもの。
部下の面倒を見てくれる上司、、、ありがたいですよね。
しかし、時としてその干渉が度を超えていくことがあります。
あまりにも細かなルール、あまりにも細かな管理、あまりにも細かな干渉、、、
育成のため!と言ってそう言うふうにする上司もいますが、その時の部下は非常に辛そうです、、、。
部下は権限が上司よりも少ない会社で同じく働いている社員ですので、奴隷ではありません。
ほどほどな距離感を保って接してあげないと、本当に部下のストレスになりかねません。
部下の長所を見ない・伸ばさない
続いては部下の長所を見ない、伸ばさないといったところです。
バランスよく短所を補っていくのは大事なことではあります。
ですが、得意な分野をひたすらに伸ばしていく方が戦力になることが多いです。
部下自身も自信がある部分を更に磨きがかかるということで、益々自分に自信を持ってもらえます。
ただ、部下の長所を見るには普段から気にしていないといけないんですけど。
部下の成長に重きを置いていない
続いては、部下の成長に重きを置いていない、です。
自分の成果や評価の方が大事だったり、会社の業績を第一に見ているときもあるでしょう。
しかし、そのせいで部下の成長に重きを置くことができないことも。
部下からして見たらそういうのは即バレしますので、あまり良いふうには思われません。
評価を自分の感覚値で決定

続いては評価基準についてです。
普通の会社であれば決められたタイミングで決められた指標に沿って人事考課が行われます。
かつ、それは定量的に行われ目に見える数字や予め立てた目標の達成度合いによります。
なるべく公平に行えるように仕組み化がされているのですが、、、その評価を自分の感覚一本で決める場合、要注意です。
よくあるのが目にかけている部下は評価がやたら高く、そうでもない部下は評価が低いというもの。
ゴマスリに弱いタイプ、、、の、上司ということです、、、。
過程を全く見ず結果しか見ない
続いては過程を全く見ず結果しか見ない、です。
仕事なので業績や結果が最重要であることは間違いありません。
成果至上主義であれば最早何も問題はありませんが、、、そんなに冷たい会社ばかりではありません。
そして成果だけじゃなくて過程を大事にしている場合も非常に多いのも事実です。
その過程こそがノウハウとなったり、ましてや再現性が高いものであればかなり重宝されます。
また、部下自身も業績だけじゃなく、そういった過程を見てもらえるのは嬉しいところですから。
自分が責任を取るのをとにかく避ける

続いては責任を避ける、です。
上司ですから、部下が行ったことの責任を取ることは当然です。
ですが、その責任を負うことを極度に嫌がり、逃げて逃げて逃げまくる上司。
もしくは更に誰かの影に入ってやり過ごそうとする上司、、、。
部下から見たらこれ以上頼りない相手はいません。
「君の代わりをいる」といった姿勢や発言をする
続いては、「君の代わりはいる」といった姿勢や発言をする上司です。
ちょっとパワハラ、もしくはモラハラな匂いもしてきますよね。
別に君が辞めたって僕は構わないよ?
といった内容ですが、これは強烈に部下のやる気を削いでしまいます。
本当にこれは言ってはいけないワーストワードです。
そもそも自分は全然働かない

最後はこちら、上司の自分は全く動かない、働かない、です。
これも先ほどの内容と同じで、割と論外な内容です。
ですが、全然働かない上司はいるんですよね。
おまけに仕事は全部部下に丸投げしてる場合は、いよいよ本格的に嫌われる傾向にあります。
部下をダメにしたデメリットは大きい

先ほどは部下をダメにしてしまう上司の例を紹介しましたが、いざ本当に部下がダメになってしまった時、かなりの自害を被る形になります。
実際にどんなことになるのかについても見て行こうと思います。
ガチで病気になる

部下をダメにしてしまった場合、それが原因で病気になってしまう可能性があります。
もちろん、全てをダメになったせいだ!と立証するのは難しいですが、ハラスメントなどの証拠を抑えられていた場合、非常に上司としても会社として不利になっていきます。
部下は病気になり、上司や会社は責任を問われるという、誰も得るものがありません。
会社を辞める
続いては部下が職場、仕事を嫌になり退職してしまうケースです。
会社は社員が辞めた場合は欠員を補充する形になりますが、その場合は採用コストが掛かります。
採用コストって社員の知り合いやツテ、自社HPでの採用ができない場合は結構費用が掛かるんですよね。
なので、上司の行いや接し方のせいで部下が退職してしまった場合、痛い出費を会社は払うことになります。
今後の部下の活躍の場を狭める

最後は部下本人の今後の活躍の場が小さくなってしまう、です。
上司が部下を育成せずに、そのまま、のほほんと作業だけを延々とやらせていた場合、今後自分で仕事を引っ張っていくことが難しくなります。
部下自身は上司がいるうちは何をするかを指示され、わからないことがあれば上司に聞けるので仕事は楽かもしれませんね。
しかし、その上司が自分の元を離れたら、自分が他の部署に移動になったら、または転職をしたら、、、
もっというと、年齢を重ねて自分が上司となり引っ張っていく立場の人間になったら、、、。
下積みの浅い、ちょっと残念な社員になってしまう未来が見えてしまう感じ、ありますよね。
部下にとっての良い上司とは?

それでは、今度はどのような上司が部下にとって良いのか、について見て行こうと思います。
これまでは部下にとっての悪い上司について見ていきましたが、良い上司は単純にその逆になっていきます。
とはいえ、これらを全て完璧にできていてハイパフォーマンスを維持し続けるのは至難です。
部下も人間なので、自分との人と人の相性もありますからね。
なので、これから紹介していく中でも全てを完璧にする、というわけではなく、少しずつできるようになり、状況や相手によって取捨選択ができれば良いのだと思います。
それでは、見ていきましょう!
状況に対しての改善案を一緒に模索する

まずは「状況に対しての改善案を一緒に模索する」です。
部下が業務上で困った場合ついつい答えをポロッと出してしまいがちですが、そのポロについては少し我慢します。
なので、ここはどういう風にして考えていけば良いのかを一緒に考えるということが重要になります。
答えを出さず、自分で辿り着けるように促す
答えを出さずに一緒に考え、、、更に【答え】に自分で辿り着けるように話を促してあげることです。
最終的に自分で【答え】に辿り着き実行するという決断までできた、ここまで出来たら超理想。
そういう【考え ⇨ 決断】までの経験は多ければ多い方がいいです。
ちなみに作業に際し想定しうるトラブル なんかも話すことができたら尚よしですね。
伸びそうな長所を見つけ更に伸ばしていく

続いては伸びそうな長所を見つける、です。
個々それぞれにやってきたことも、考え方も、得意なことも違っていきます。
最初から得意なものがわかっている部下もいれば、仕事をしていく中で目覚ましい成長をしていくこともあるでしょう。(覚醒したな、あいつ。みたいな)
個々の長所は組織にとっての大きな武器になっていくので、ぜひ伸ばしていきたいところ。
自らが積極的にコミュニケーションを取る、でもいいですし、組織内で簡単なアンケートを取って他面評価で情報を得るのもいいでしょう。
部署によってはその長所を100%活かして!というのは難しいかもしれませんが、、、部下が活かすことのできる長所を是非見つけてあげてください。
業務を通して部下が成長できるかを考える
続いては業務を通じて部下が成長できるかを考える、です。
これはかなり曖昧な感じなんですが、、、
現段階では少し力が足りていないプロジェクトや業務に携わってもらう、というのが一番イメージしやすいかと思います。
なので、部下自身が勉強をしたり、必死に業務に食らいつくといったことが求められ、結果的に成長に繋がります。
延々と電話番、印刷係、もしくは原票等の打ち込みじゃあ、、、、全く成長はしないというのはイメージできるかと思います。
評価は定量評価を公平な立場で行う

続いての評価は定量評価を公平な立場で行う、です。
感覚で評価をするのではなく、しっかりと数字で見えるように評価しようね、ということ。
恐らく多くは、最初の目標設定等の段階で定量的な目標設定をしているのではないでしょうか。
なので、設定した目標に対しての達成度合いを見ていくことが重要です。
もちろん、新規で取り組んだことに対して結果が出なかったとしたら、その過程や頑張っていた熱意を評価するのはありだと思います。
しかし、これをやる時は全ての部下にも同様にする必要があります。
じゃないと

って、なりますよね。(実際になったことのある人も多いのでは、、?)
結果は大事!しかし過程も超大事
社会人として、組織として見られるのは結局のところ【数字】です。
どれだけ売り上げを出したのか、、どれほど損失を防いでいるのか、、、
どれほど頑張っても結局のところこの【数字】が全て、ということも大いにあるでしょう。
ですが数字を出すには何かしらの考えがなければいけませんし、実行時には工夫もしているはずです。
そういう意味で言えば、仮に会社の評価として結果が届いていなかったとしても、上司はしっかりと部下の過程の働きを評価しなくてはいけません。
それこそ結果も出なくて過程も見てもらえなかった場合って、モチベーション下がりまくって、むしろマイナスに突入ですからね、、、。
責任を持つ、または姿勢を見せる

続いては部下の仕事に責任を持つ、または姿勢を見せる、です。

おおおおおおお〜〜い!!!!!ですよねw
組織構造上、下の失敗は上が責任を取るのが一般的ですが、上司はこれを結構嫌がります。
俺の評価が下がるだろ!!!と、言う人もいるほどですが、こういう上司は漏れなく嫌われていましたね。
上司は上司の務めとして、部下の行動に責任を持ってあげてください。
個人の存在を最大限認める
続いては個人の存在を最大限認める、です。

と、嘘でもいいから言ってもいいと思います。
人は自分を認めてもらいたいですし、認めてもらえないところで頑張ろうと思うことはできません。
躍起になってやる気を出す場合もありますが、、、まぁ長続きはしないでしょう。
そんなことに力を入れるくらいであれば、その分を業務の方に力を入れてほしいですからね。
なので【このチームには君が必要】と言うことをしっかりと伝わる形で伝えると言うのが大切です。
ただし、、、微妙にセクハラになりかねないところでもありますので、その辺りは慎重にした方がいいですが、、、。
部下は見ている!自分もしっかりと働く

最後は【自分もしっかりと働く】です。
部下は、というか人は上を見て育ちます。
上が誰かの文句を言っていれば文句を言いますし
上が仕事を適当にやっていたら適当にやりますし
上が働かなかったら当然働きません。
悪いところ見るな、自分のいいところだけを見ろ!は、都合が良すぎるんですよね。
自分の思っている以上に部下は上を見て、学び、同時に上を評価しています。
いわゆる【ミラーリング】と言うものになりますが、こちらについては別記事でも記載していますので、よかったらこちらもご参照ください。
一番の部下へ害悪は、、、【一切関与しないこと】

ここまでは部下にとっての悪い上司といい上司について見ていきました。
最後に一番最悪な上司について見ていきます。
それは【一切関与しないこと】です。
部下を叱りも褒めもせず、業務にも関与せず、、、一体なんのためにいるのか?状態です。
逆に【一切関与しない方がいい】と言う意見もあると思います。
その意見も実はわからなくはありません。
ただし、それは部下が既に【自らが主体的に考えて動くことができる】と言う条件下のみだと思います。
もう本当に優秀で独立できている場合のみです。
多くの場合はそうではなく、むしろ【自らが主体的に考えて動くことができる】ようにサポートをしていかなければなりません。
しかし、部下ができるからといって【一切関与しない】はあり得ません。
上司の務めの全てを放棄した【一切関与しない】は、最悪の悪手です。
部下を活かすためにできることを
以上が部下をダメにする上司、それからいい上司についても書いていきました。
全てを完璧にできるスーパー上司になるのは難しいです。
しかし、知らず知らずのうちにやってしまっているものは是正していき、逆にできることを少しずつ行っていけばいいんです。
上司だって完璧な人間じゃありませんので、部下と一緒に成長していくのがいいですよね。
長くなりましたが最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは、また。
【こちらもオススメ】